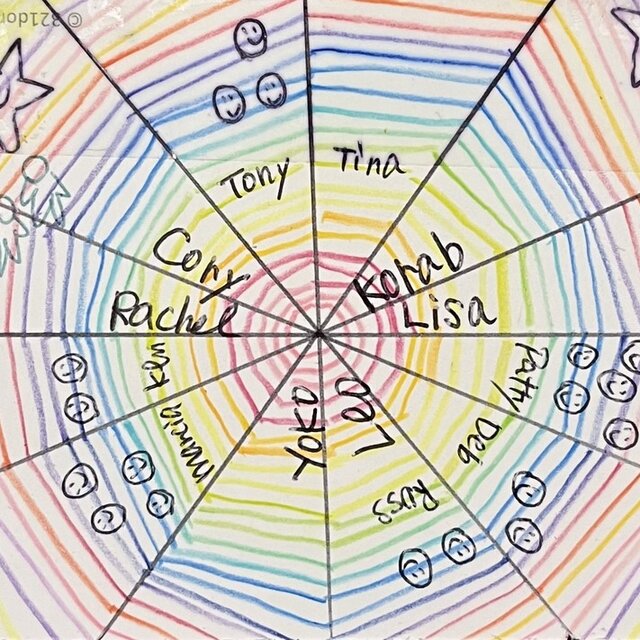「喜べ、幸いなる魂よ」
2023年に第74回読売文学賞を受賞した本作は、18世紀のベルギー、フランドル地方の亜麻糸商の家を舞台に、結婚や家庭というものに縛られず、自立を目指した女性ヤネケと、彼女を生涯かけて愛し続けた素朴な男ヤンの物語である。女は男のもとに嫁ぎ、子供を産むことが義務だと考えられていた時代に、ヤネケは結婚することなくヤンの子を産んだ後、女性だけの共同生活団体“ベギン会“に入り、数学や経済学の研究に没頭する。
ベギン会とは
中世ヨーロッパの封建的社会において、女性が独身でいることは許されず、結婚するか修道女となるしか選択肢は無かった。そんな中で、13世紀のベルギー北西部のフランドル地方で設立されたベギン会は、未婚や夫に先立たれた女性たちによる、女性のみで作られた互助組織である。壁に囲われた敷地内には、住宅、教会、診療所などがあり、彼女たちは日々の祈りを捧げながら清貧な共同生活を旨とした。それは修道女とは異なる半聖半俗の生き方で、退会すれば結婚も可能であった。様々な境遇の女性達が、助け合いながら質素で規律正しい生活を送りつつ、自立するためにレース編みや教師などの仕事をして収入を得ていた。自分の才能や技術で自立したいという女性の多様な生き方を支える組織が、こんな昔にベルギーという国に多く作られたというのは驚きである。
ベギンとして生きる道を選んだ、逞しく魅力的なヤネケたちの姿が、本作では生き生きと描かれている。
女性としての不自由さ
亜麻糸商の家に、男女の双子の姉として生まれたヤネケは、小さい時から恐ろしく頭が良く、弟のテオは「姉ちゃんが男だったら、ルーヴェンの大学に行って博士様になる」といつも言っていた。好奇心旺盛で、何でも実験してみないと気が済まないヤネケは、兎がやっていた交尾が自分たちにも出来るのかという実験に挑む。協力させられたのは、この家に引き取られ兄妹のように育てられたヤン。その結果ヤネケは妊娠する。
ゲントにある知り合いの家にこっそり送られたヤネケは、山積みの本の中で勉学に勤しみ、ルーヴェンの学校に通うテオの論文の代筆をしながら、無事男の子を産む。そして我が子を里子に出すと、家には帰らずに、たくさんの本と共にベギン会に移り住んでしまう。家に帰ってしまったら、勉強を続けることは出来ないと考えた末の決断だった。女の名前で数学の本は出せないし、大学にも行けない。そこで弟テオの名で本を出版し、彼が運河に落ちて亡くなると、今度はヤンの名で様々な本を出し、ヨーロッパ中の相手と文通するようになった。もちろん自分はベギンの女性であることは隠して。
男性としての不自由さ
養子でありながら家を継いだヤンは、ヤネケの産んだ子レオを引き取り育てる。そしてテオが亡くなると、彼の妻だったカタリーナと結婚し、彼らの子も大切に育てる。しかしヤンは、ずっとヤネケのことを、ただひたすら愛し続けていた。男としてのプライドや葛藤を胸の中に閉じ込め、家を守り多くの子供を育て上げたヤン。家庭や子育てよりも、自分のやりたい事を優先して、勉学に生涯を捧げた女性ヤネケ。この男女逆転の構図は面白い。ヤンがヤネケを愛し続けられたのは、誰よりも彼女の本質を見抜いていたからであろう。
現在のベギン会
2022年の10月と2023年の4月にベルギーを訪れた際、ルーヴェンのベギン会大修道院と、街の北にあるリトル・ベギン、そしてブルージュのベギン会修道院に足を運んでみた。世界遺産でもあるルーヴェンのベギン会大修道院は、敷地の中にレンガ造りの家や教会や広場があり、ひとつの完成された小さな街のようである。川が流れる美しい石畳の小道。その静かな佇まいの中に身を置いていると、まるで中世にタイムスリップしたような気分になる。20世紀に入り、女性の社会進出とともにベギン会は衰退し、最後のベギンの女性が亡くなった後、現在はルーヴェンカトリック大学の教員や学生たちが住んでいるとのこと。中の様子は分からないが、昔の女性に合わせたのか住まいの入り口は小さく、今の背の高いベルギー人が暮らすには、少し窮屈かもしれない。それにしても、何百年も前に造られた建物を、当時のままに美しさを保ち、それを生活のために大切に使い続けているベルギーの人たちには感心する。
作家について
男尊女卑の考え方が徹底していたこの時代、女性が自立し自分の意思で生き方を選択できた驚くべきシステム“ベギン会“という組織。そこから壮大な物語を紡ぎ出したのは、大学で西洋美術史を学び、日本より欧州に親しみを覚えると語る作家、佐藤亜紀さん。話は18世紀のベルギーでありながら、登場人物の生き様が実に生き生きと描かれ、彼らの葛藤や希望がすんなりと心に響いた。ベギンの慎ましくも自由な生き方は、自立を目指す女性たちに、希望の光を与えたのは間違いない。生きづらい時代の中でも、軽やかに信念を持って生きぬく女性たちの姿が印象的な本作、ぜひ手に取ってもらいたい。
終わりに
ベルギーを舞台にしたおススメ映画を2本。
「ヒットマンズ・レクイエム 」マーティン・マクドナー監督 2008年 英米合作ベギン会修道院があるベルギーの古都ブルージュが舞台。ロンドンでひと仕事終えたばかりの、新米殺し屋レイとベテラン殺し屋ケン。2人はボスからブルージュでの潜伏を命じられる。歴史や文化を愛するケンは観光を楽しむが、レイは全く興味が無い。ボスの命令を聞いたケンがとった行動とは?驚きの展開と皮肉な結末。ブルージュの美しい街並みや運河、聖血礼拝堂など観光名所もしっかり見せてくれ、殺し屋たちの悲しい宿命も味わえる。
「トリとロキタ」ジャン=ピエール・ダルデンヌ+リュック・ダルデンヌ監督 2022年 ベルギー仏合作長年に渡りベルギーの移民問題に光を当ててきた、ベルギー、リエージュ出身の監督ダルデンヌ兄弟。本作はそのリエージュを舞台に、アフリカから密航してきた身よりの無い少女ロキタ(10代後半)とトリ(10歳ぐらい)の家族を超えた深い結びつきを描く。偽造ビザを手に入れる為に、どんどん危険な仕事に手を染めていくロキタと、彼女を助けようとするトリの姿に心が痛む。
私自身がベルギー滞在中に、地域にもよるが実に多くの移民の人たちを見かけた。帰国して本作を鑑賞し、駅や街角で身を寄せ合っていた彼らは、果たして本当の家族だったのだろうかという疑問がよぎった。30年近く移民問題に目を向け、彼らの過酷な日常を淡々とした演出で描き続けてきたダルデンヌ兄弟。しかし、今現在も彼らを取り巻く環境が変わっていないことは、悲しく憤りを感じる。
東京在住。年間500本以上を鑑賞する映画中毒。好きな監督はミヒャエル・ハネケ、ラース・フォン・トリアー、デヴィッド・クローネンバーグ。人間の本質を深く抉った作品が大好物。