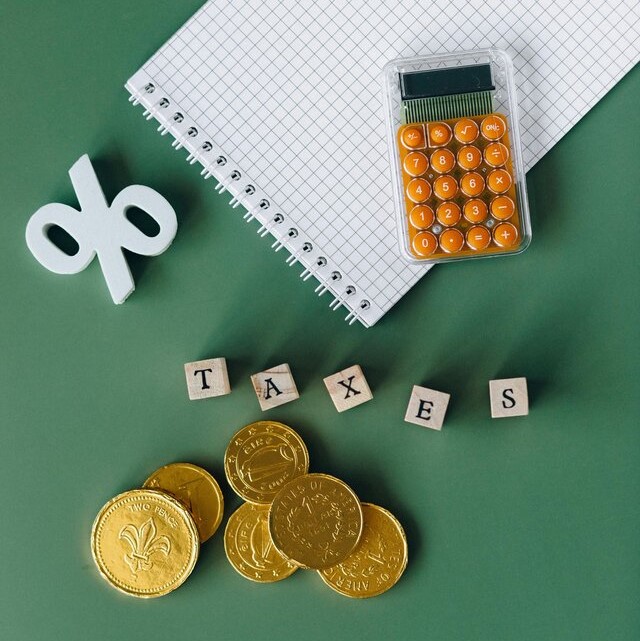トランプ政権と向き合うイギリスとNATO
第二次世界大戦以降、アメリカは常に世界を動かす大国であった。アメリカが中心となって築いた自由・平等、民主主義、市場主義に根差した世界秩序はより多くの国に繁栄や平和をもたらし、アメリカは同国を敵とみなす国の人々にとってもあこがれの国だった。しかし、トランプ大統領の二期目が始まり、その世界秩序も世界がアメリカに対して抱いていた尊敬や憧れもこわしつつある。
トランプのアメリカは人種や性、宗教上の差別をすすめ、自分に盲目的に従わない人々を攻撃し社会的な排除を試み、自らが恨みを抱く人々に不当に報復し、法を無視し、同盟国といえども脅しによる搾取を図る。
4月はじめにはとうとう世界各国を対象とした高税率の関税を発表した。根拠のない数字を元にアメリカが長年不当な貿易慣習の犠牲になってきたと主張し、敵視する中国はもちろん、同盟国でも日本24%、EU20%、台湾32%、スイス31%と高率を課した。対象となった各国の経済はもちろん、アメリカの市民生活にも大打撃となるだろうが、トランプ大統領はそれすら他国の責任とし、関税を交渉の武器として、各国が自分に従属することを求めているかのようである。
トランプ政権でも生きる「特別な関係」
その中でイギリスへの関税は10%と発表された。イギリスも他の同盟国同様第二次トランプ政権に惑わされ、どう付き合うべきか苦悩している。関税10%はイギリス経済に打撃を与えるといえども、日本はもちろんEUより低いのはスターマー政権(労働党)のトランプ大統領対応作戦と「特別な関係」が功を奏したといえる。
英米の「特別な関係」は、歴代の英首相とアメリカ大統領の密接な関係が他国にも見えるもっとも鮮明な形である。しかしそれを強固にしているのは、外交はもちろん核戦略を含む軍事関係そして諜報関係である。
英外相の机には世界に数多くある国の中で唯一、米国務長官との直通電話があり、両国は国連でもNATO(北大西洋条約機構)でも他国がうらやみ同時にねたむ強い連携を培ってきた。NATOの総司令官は歴代アメリカ人、そして多くの場合No2は英国の軍人であった。安全保障に欠かせない諜報分野では通信傍受や暗号解読を担うNSA(米国家安全保障局)と英国のGCHQ(政府通信本部)は第二次世界大戦中から切っても切れない協力関係を築いてきた。それだけに国際秩序を共に築き、冷戦をはじめ多くの戦いをともに経験し、親友どころか親族ともいえたアメリカの豹変ぶりは衝撃どころでない。ウィリアム・ヘーグ元首相(保守党)は、英国の政治家、軍人、スパイ、外交官たちは米政権の激変にめまいを起こしていると記している。
スターマー首相の対トランプ戦略は、表面上はあくまでも穏やかに、決して大統領を批判しない、一方裏では事実を積み上げ、粘り強くNATOのウクライナ支援や二国間貿易協定に関する説得を続けてきた。そしてトランプ大統領が拒絶できない「人参」もぶら下げた。チャールス国王からの公式訪問の招待である。トランプ大統領は多くのアメリカ人同様、英王室には強い憧れがあり、母がスコットランド生まれであったことを誇りにし、同地にゴルフ場を所有しそこでプレーもしている。スターマー首相は、英国王が王室の避暑地であるスコットランド・バルモラル宮殿にお招きすることも検討していると伝えてトランプ大統領の心を揺さぶった。バルモラル宮殿はヴィクトリア女王にはじまり英王室が最も愛する宮殿で、外国の指導者が招待されることはめったにない。
トランプ政権がもたらす脅威
トランプ大統領はNATOからの撤退の可能性に繰り返し言及し、負担金を増やさなければ攻撃されても防衛しないと加盟国を脅してきた。一方ではウクライナに侵攻し、人命も国際法も意に介さないプーチン・ロシア大統領にはしばし同調し、対ロ制裁を緩和するかもしれない。グリーンランドとカナダを強引に領土にし、パナマ運河を支配しようとまでしている。ウクライナをロシアに売り飛ばすのではないか、米ロ中で「第二のヤルタ」ともいえる三か国による世界分割統治を図るのではないか、といった不安も広がっている。
その中で米政権の中枢メンバーが「シグナル」という民間アプリでイエメンの武装集団フーシ派への攻撃を検討し、軍事作戦について語ったのは諜報を共有するファイブ・アイズ(英、米、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド)、特にイギリスには衝撃であった。諜報や安全保障にかかわる通信は、最高の秘匿性を有する政府公式機種やソフトを使用するという基本ルールが破られたのみならず、大統領も関係者もそうしたルールの重要性を認める様子もない。米英関係の最も強力な接着剤ともいえる諜報共有に大きな不安が生じたことになる。
トランプ大統領ばかりか政権中枢メンバーの欧州に対する憎しみともいえる感情、すべてをゼロサムでのみ計る商業主義もシグナルでの交信が赤裸々にさらした。フーシ派はイスラエルを支援する西側の船舶を攻撃していたが、ミラー大統領次席補佐官とウォルツ国家安全保障担当補佐官は攻撃にかかった費用を欧州に払わせるべき、バンス副大統領もヘグセス国防長官も欧州を「救済」すべきでない、「欧州のただ乗りは憎々しい。あざとい」とまで述べている。
イギリスやNATOの対応
欧州のNATO加盟国はアメリカ抜きのNATOを真剣に検討せざるを得なくなっている。しかし、ウクライナへの支援だけを見ても、武器弾薬はある程度補えても領土防衛のための最先端ミサイル装備、そしてなんといっても諜報はアメリカ以外はほとんど提供できない。アメリカからの情報がなければ、どこに攻撃ドローンを飛ばすか、敵がどこから攻めてくるかもわからない。通信もイーロン・マスクのスターリンクに頼っている。
こうした状況にかんがみ、欧州のNATO加盟国はミサイル運用や諜報に欠かせない独自の衛星ネットワークの構築を計画し、自国の防衛費を増加させ、ARRC(連合緊急対応軍団)を強化させている。こうした政策はアメリカのNATOへのコミットメントを繋ぎとめるためでもある。
また欧州内の地域防衛で欧州加盟国のみでの対応を図っている。北極圏がロシアや中国、アメリカの勢力圏争いの舞台になりつつあり、バルト海ではロシアや中国が海底装備を破壊している。そこで地域防衛のための統合遠征軍が編成されたが、メンバーはイギリス、北欧諸国、バルト諸国そしてオランダである。NATOも「バルティック・センチュリー」というバルト海をパトロールする作戦を発表したが、運用を担っているのは欧州加盟国である。フィンランドとスウェーデンがNATOに加盟し、この地域の防衛を担う国が増えた。しかし、それでも戦艦の数すら十分ではないのも事実である。
とはいってもアメリカに頼り過ぎ、防衛産業や通信を含む先端技術への投資や育成を十分にしてこなかった欧州加盟国が欧州として持つ力をプールし、協力し、発展させる方向に大きく一歩を踏み出したのは間違いない。
イギリスはトランプ大統領の英王室への憧れ、トランプ大統領が目の敵とするEUから脱退したこと、そして築いてきた「特別な関係」を活用し、他の同盟国や地域に先んじ米英自由経済協定の締結も視野にいれている。
同時にアメリカと欧州の橋渡し役を果たすことで欧州との関係強化も図っている。一度は決別したトランプ大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領の関係を修復し、欧州のウクライナ支援策をまとめたのもイギリスである。
トランプ大統領に表立って喧嘩を売るのも、従僕のような姿勢を見せるのも得策ではない。強みを生かし、自助努力をし、プライベートではアメリカの置かれた状況への理解を示しながらも堂々と渡り合う強さを見せなければならない。
日本の金融機関に勤めた後、国際問題を学ぶためマサチューセッツ州のフレッチャー外交法律大学院へ。卒業後ワシントンとロンドンを行き来し、外交安全保障問題やNATOなど同盟関係に関し日本のメディアやシンクタンクに執筆している。