J.D.ヴァンス著「ヒルビリー・エレジー アメリカの繁栄から取り残された白人たち」
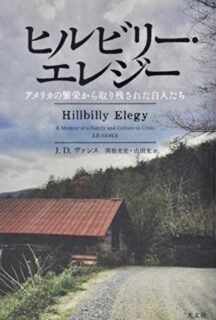
「ヒルビリー・エレジー アメリカの繁栄から取り残された白人たち」
J.D.ヴァンス著
関根光宏・山田文訳 光文社
本書は2016年6月に米国で出版されたHillbilly Elegyの訳本である。同年のトランプ政権誕生と相まって大いに注目を集めたそうだが、筆者はごく最近まで本書のことは全く知らなかった。本年1月トランプ派による連邦議会議事堂への襲撃が世界の耳目を集めた直後、偶然にも日本とアメリカそれぞれの友人から勧められた。本書が2020年秋に映画化され、Netflixで配信され始めたこともきっかけになっているのかもしれない。
本書は、著者J.D.ヴァンスがヒルビリーの一員としてどのような子供時代、少年時代を過ごしたかを描くとともに、ヒルビリーに代表される白人労働者階級の人々が抱える深刻な問題と考え方を紹介している。そして著者自身はそのような環境に育ちながらも州立大学に進み、イェール大学のロースクールを卒業するまでになるのだが、そのきっかけとなったものが何かを描いている。
ヒルビリーとアパラチア山脈
ヒルビリーとはどのような人のことを言うのだろう。本書の中で著者は次のように解説する。「『スコッツ=アイリッシュ』の家系に属し、大学を卒業せずに労働者階層の一員として働く白人アメリカ人。先祖は南部の奴隷経済時代に日雇い労働者として働き、その後はシェアクロッパー(物納小作人)、続いて炭鉱労働者になった。近年では機械工や工場労働者として生計を立てている。アメリカ社会では、彼らは 『ヒルビリー(田舎者)』、『レッドネック(首すじが赤く日焼けした白人労働者)』、『ホワイト・トラッシュ(白いゴミ)』 と呼ばれている」。地理的には18世紀に移民としてやって来て、アパラチア山脈の山中に住み着いた人々を指したという。アパラチア山脈は、南はアラバマ州やジョージア州から、北はオハイオ州やニューヨーク州の一部に及ぶ広大な地域である。
著者J.D.ヴァンスにとっての故郷
著者はオハイオ州ミドルタウンで生まれ育った。しかし、彼にとって家(ホーム)と呼べる場所は、アパラチア山脈の東部にあるケンタッキー州ブレシット郡のジャクソンという町だという。著者の母方の祖母の生まれ故郷であり、毎年のように祖母や姉と一緒に訪れていた場所だ。ジャクソンには祖母の母 「ブラントンばあちゃん」 の家があり親戚も周囲に数多く住んでいたので、いとこたちと山や谷を走り回り子供らしい時間を過ごすことができた。また伯父たちが様々な話をしてくれた。例えば、悪と見なされた事柄に対し凄惨な裁きが行われたことからその地域一体が 「血みどろのブレシット」 と呼ばれるようになったこと、一族の人々が家族を守るために極端ともいえる行動を取ったというエピソードなど。そうした話を聞いて、著者もその一員であることに誇りを感じていた。また、ジャクソンでは誰もがお互いに挨拶をし、葬列があると皆が車から下りて霊柩車を見送るという風習があった。そんな時、著者はまさに自分がヒルビリーの一員であると自覚したのだという。
オハイオ州ミドルタウン
著者の祖父母は若い時に駆け落ちをして、ケンタッキーからこの町にやって来た。祖父はアームコという大手鉄鋼会社に職を得たが(後にアームコは日本の川崎製鉄と合併してAKスチールになる)、そこには多くのアパラチア出身の人々が働いていた。1940-50年代にかけてアパラチアから中西部産業地帯には、こうした企業で働くために多くのヒルビリーたちが移住したのである。ヒルビリーは住む場所が変わっても自分たちの暮らし方を変えることがなかったので、もともといた住民との間に軋轢を起こし、それが彼らへの偏見の源にもなった。たとえば、祖母の親しい友人の一人は家の裏でニワトリを飼っていたが、ニワトリの数が増えると裏庭で古参のニワトリの首を絞めて食べるために処理する。そのため隣人は、鳴きわめくニワトリが首を絞められるのを数メートル先で目撃させられるという具合だ。
著者にとってオハイオ州ミドルタウンでの暮らしは決して楽しいものではなかった。看護師である母親が結婚と離婚を繰り返したために父親や住む場所がしょっちゅう変わったことと、子どもに対する愛情はあるものの、薬物依存が原因で母の態度は何度も豹変するからだった。そんな生活の中で、著者を一貫して支えていたのは祖母だった。口が悪いが恐ろしく正義感が強く、著者に 「お前はなんだってなりたいものになれるんだ」 と繰り返し、宿題を済ませたかとうるさく尋ね、アルバイトを奨励し、温かい安定した環境を与えてくれた。母や父たちとの生活に疲れ果てた著者が祖母の元で過ごした高校時代の3年間が彼を大きく成長させたのである。
海兵隊、大学進学を通して見えたもの
高校を卒業する頃には著者は大学進学を希望するようになっていたが、届いた分厚い申請書類を見て青くなる。直系の家族の中に大学進学をした人がいないので記入の仕方も学資援助の選び方もわからなかったのである。大学生活をどう送ればいいかにも自信がなく迷っていた著者は、いとこの勧めで海兵隊に入隊する。そこで彼は規律正しい生活とともに健康や衛生意識、金銭管理についても学び、さらには強い意志を持って行動するということを学ぶ。
海兵隊の任務を終えて著者はオハイオ州立大学に入学するが、海兵隊で身につけた自信と物事を計画的に進める能力のおかげで、その後見事イェール大学のロースクール入学を果たす。そうした自身の成長を経て、彼にはヒルビリーの人々の抱える問題がはっきりと見えるようになっていく。例えば、ロースクール進学の費用を稼ぐためのアルバイト先で目にしたのは、まじめに取り組めばそこそこの暮らしが保証される仕事を手にしながら、度重なる欠勤や無責任な勤務態度でみすみすその機会を逃してしまう若者たち。ケンタッキーでもオハイオでもヒルビリーの社会に共通するのは、失敗の責任を自分以外の人や物に押し付けること、借金をしてでも高額の商品を買ってしまうこと、薬物依存症、不安定な家庭などである。
著者はロースクール時代にあることがきっかけで、自分のような環境で育った子どもが陥りやすい様々な問題行動が、心理学者によって重要なテーマとして研究されていることを知る。親から悪態をつかれたり、ののしられたり、侮辱されたことや、両親の別居あるいは離婚を経験していること、アルコール依存者または薬物依存者と同居していたことなどの逆境的児童期体験(Adverse childhood experience, ACE)がトラウマ体験として大人になっても続いてしまうのだ。自分の体験はまさにヒルビリーの家庭で繰り返されている状況だったのである。
最後に
最終章のタイトルは 「何がヒルビリーを救うのか」 である。はっきりと具体策が挙げられているわけではない。ただ、著者は今まで自分に手を差し伸べてくれた人たちを列挙し(その中には祖母はもちろんだが、薬物依存ではあったものの教育熱心だった母も含まれている)、その誰が欠けても今の自分はないだろうと断言する。そして逆境に打ち勝って成功を収めた人たちからも同じような話を何度も聞いたそうだ。信頼できる家族がいることがすべての始まりなのだろう。海兵隊に入り自分自身をコントロールする力を身に付けた著者だが、その基礎にあったのは、やはり祖母から受けた常に変わらない愛情だったのではないかと思う。逆に言えば、ヒルビリーに生まれて信頼できる家族や安定した愛情に恵まれなかった時、あるいは壮絶な逆境的児童期体験があった場合、人々は不幸の連鎖の末、自分をコントロールできないことや勤勉に努力できないことを全て他人のせいにしようとするのだろうか。それがまさに前大統領のような人物に惹かれる人々が大勢いることの理由の一つなのだろうか、と考えてしまうのである。
本書の巻末に、米国ボストン在住の翻訳家・書評家である渡辺由佳里氏が解説を書いている。2015‐2016年の大統領選挙戦期間中、トランプを含む様々な候補者の集会に自ら足を運び、候補者ごとに集会のスタイルも支持者も大きく違うことを肌身で感じたそうである。トランプを冗談候補とあざ笑っていた政治のプロたちが、トランプが予備選に勝ちそうになって慌てて手に取ったのが本書だったと明かしている。解説は13ページに及び、これ自体もなかなか読み応えのあるものだった。結びの文が大変印象的だったので引用させていただく。
「50年後のアメリカ人が2016年を振り返るとき、本書は必ず参考文献として残っていることだろう」――。
神戸大学在学中第31回日米学生会議に参加。1989~1995年夫の転勤に伴い英国在住。2000年より練馬区役所、2013年より東京都庁の双方で外国人相談員を務める。2018年4月より2020年6月までワシントンDC在住。ワシントン日米協会おはなし会ボランティア、日米協会ナショナルジャパンボウル委員会委員を務めた。


