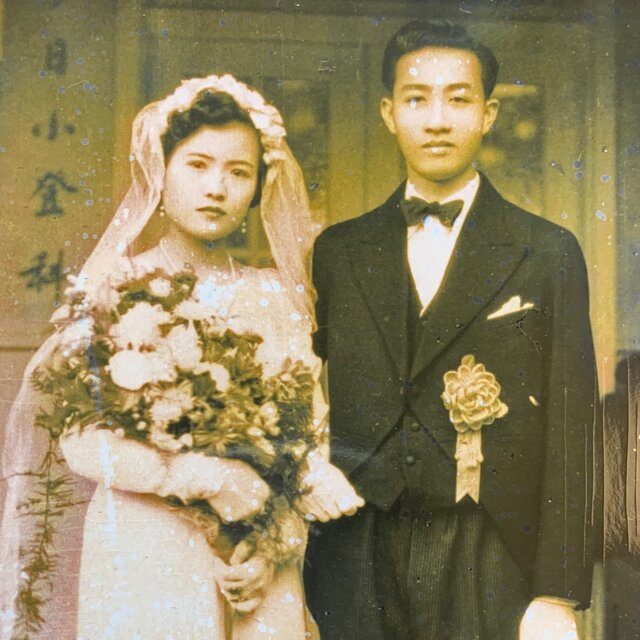岡倉覚三(天心)著『茶の本』(村岡 博訳 岩波文庫)

岡倉覚三(天心)著『茶の本』村岡 博訳 岩波文庫
まず、本書に出会ったことをありがたく思う。本書は1906年に、同著者により英文で出版されたThe Book of Teaの訳本で、もともとは西洋人のために書かれた本である。名画をわからぬ人に、絵を見せることなく名画である所以をしたためたごとき本書が、当時の西洋人にいかに受け入れられたのか興味深い。筆者にとっては、別次元に押しやられていた和の心に滋養をいただいたような満足感が残った。
本文では著者を、馴染みのある「天心」と呼ばせていただく。天心は、幕末の西洋化が進む中、近代日本美術の発展に寄与し、西洋と東洋の精神性の融和を図った人物として知られているが、本書には、一杯の茶に凝縮された天心の美意識と世界観が耽美的でオーガニックに浮き彫りにされている。英文のオリジナルと訳を合わせ読んだが、和訳は文学性が高く、美しさに心が震える場所が多々あった。
信念固きロマンチスト
原本のThe Book of Teaは、天心がボストン美術館の中国日本美術部長として日本とアメリカを行き来していた時期に書かれている。誇る地位を得ながらも母国への郷愁を抱き、東洋人と西洋人の資質を比較していた時期でもある。「おのれに存する偉大なるものの小を感ずることのできない人は、他人に存する小なるものの偉大を見逃しがちである」と、西洋人と日本人の機微の差を示唆している。
西洋人にとって茶道は「東洋人の珍奇」に映ったであろうと言いながら、天心は茶道の深みを驚くほど端的に表現している。「茶は日常生活の俗事の中に存在する美しきものを崇拝することに基づく一種の儀式であって、純粋と調和、相互愛の神秘を諄々と教えるもの」であり、「不完全なものを崇拝するにある」と定義している。天心は、茶道の信者を「趣味上の貴族」と呼んだ。日本人の縦糸に潜む繊細、かつ高尚な精神性を西洋に伝えようとしたロマンが見える。
芸術の息吹が宿る聖堂
天心は「茶は芸術」であり、茶を点てる人の「独自の話ぶり」に真の美が存すると言っている。「話ぶり」とは、亭主による室礼の趣味や所作、客との短い会話のすべてがかもし出す、おもてなしの趣のことと察する。茶の極意を追求する茶人達は「ただの芸術家以上のもの、すなわち芸術そのもの」になろうと努めていたという。
茶の演出の話では、天心の幽玄の世界と理論が交差していておもしろい。待合から茶室に通じる露地について紹介すると、露地を渡ることは「自己照明 – self-illumination (英文)」に達する行為で「黙想の第一段階」と言っている。落ち葉、木漏れ日、不揃いな庭石や苔むした石灯籠は、「やわらかい霊光の無我の境地に浸って、渺茫たる彼方に横たわる自由を憧れる新たに目覚めた心境」を起こそうとする演出であり、それが露地をつくる奥意と言っている。このような心持ちで黙々と「聖堂」つまり茶室に近づいて行く客は、千利休の時代の武士であれば、にじり口から入る前に刀を外すことがごく自然な行為だったに違いない。
天心による茶室の描写は、読み手を凛とした高尚な空間に入った気持ちにさせる。松風と呼ばれる釜の音が聞こえてくるし、小さな白い麻の茶巾がお役目を待って、薄明かりの中に光っているのが見える。いったん茶室に入れば身分の差はなく「芸術的精神と自由に交通する唯一の機会」を与えてくれる空間となった。天心の時代において、「いっそう茶室を必要とする時代」になったと、殺伐とした人の心を嘆いているのは興味深い。
花に至っては「我々は純潔と清楚に身を捧げることによって、(花をちぎることの)罪滅ぼしをしよう」と、人と花との譲り合いを取り決めている。それに対して、西洋で舞踏会の翌日に捨てられる花の量は一大陸を飾るほどと言って、西洋人の花の命を物ともせぬ姿勢を中傷している。
茶道は道教の仮の姿
本書では、茶が洗練されて行く歴史の中で、一つの礎となった「茶経」が紹介されている。唐朝時代の陸羽による書物だが、その内容の具体性には驚く。例えば、水源による水の格付け、製茶器具の選別、お湯の湧き具合と使用するタイミングに至るまで詳細が記されている。茶の種類と茶器の相性に関するウンチクもなるほどと思う。団茶(固形茶)には青色茶碗を理想的としたのに対して、粉茶には濃藍色か黒褐色の重たい茶碗がふさわしいとされている。
天心は「日本の茶の湯において、茶の理想の極点」を見た。道教の教えや宇宙の法則など、茶の湯の精神が培われた過程をあれこれ論じた上で、そう結論付けている。いにしえの茶人達の試行錯誤には何一つ無駄が無く、時空を超えて辿り着いた形が、日本の茶の湯だと言いたいのだろう。最後に「調和を乱す一指の乱れもなく、統一を破る一言も発せず、すべての行動を単純に自然に行うのが茶の湯の目的で、(中略)その背後には微妙な哲理が潜んでいた」、「茶道は道教の仮の姿であった」と締めくくっている。
大宇宙と小宇宙
「茶は、宇宙に対する我々の比例感を定義する精神幾何学」という難しい言い方もしている。茶の湯にかかわる全てが、大宇宙の真理に寄り添う相似形の小宇宙ということだろうか。最後の章で利休の小宇宙にも触れている。秀吉から「自己犠牲 – self-immolation (英文)」を仰せつかった利休の最期をもって、美の権現を追究したと言われる利休の小宇宙が完成するのかもしれない。「大宗匠らは常に宇宙の大調和と和しようと努め、いつでも冥土へ行く覚悟をしていた」と言い、利休が白装束で短剣を抜く前に詠んだと言われる絶唱をもって、「茶の本」を終えている。
ワシントン在住。日米のかけ橋となる仕事、ボランティアに関わっている。趣味は芸術鑑賞。